教授

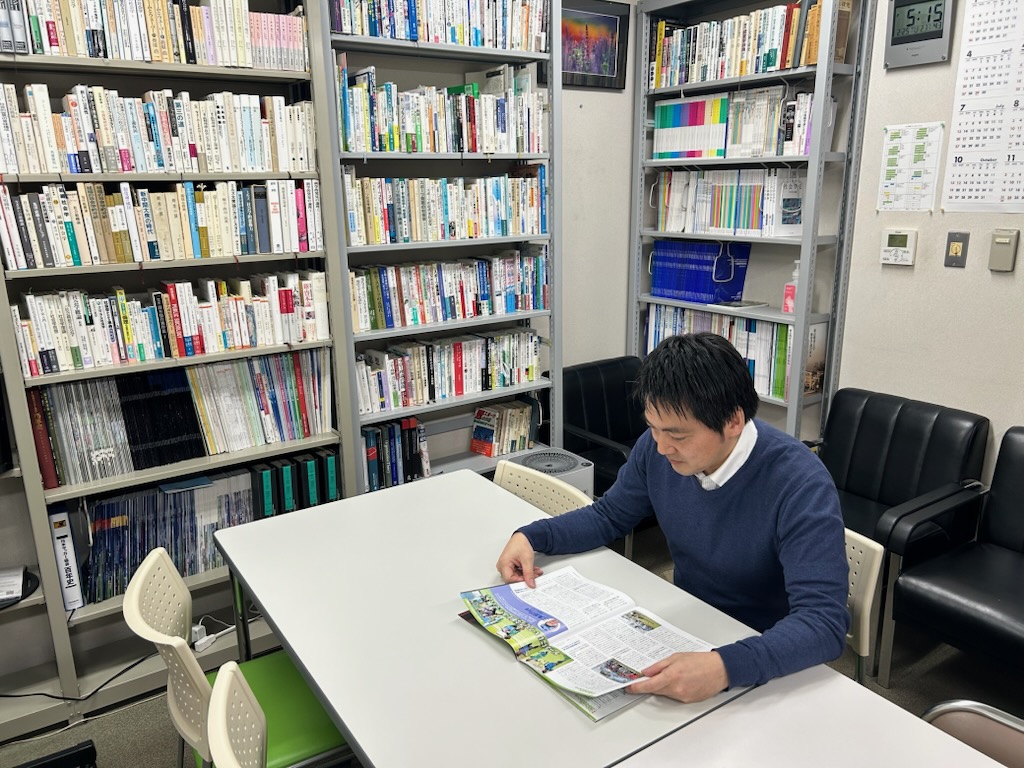
担当授業
スポーツ社会学 / スポーツ文化論 / スポーツ科学社会実装演習Ⅰ /スポーツキャリア演習Ⅲ・Ⅳ / スポーツ専門演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
受験生・学生へのメッセージ
現代社会のなかで、スポーツにかかわらないようにすることの方が難しいといわれるほどスポーツはみなさんの生活に大きく影響を及ぼす存在になってきています。例えば、初めて会った社会人同士の会話で、最初に話題になるのが天気の話(「最近の夏は猛暑で異常気象ですね~」など)で、次に話題になるのがスポーツの話(「大谷が昨日もホームランを打ちましたね~」など)だと言われることがあります。また、SNS・テレビ・インターネット・雑誌・新聞などのメディアを通して、日々多くのスポーツに関係する情報が発信され、知らない間にスポーツに触れていることも多々あると思います。これらの情報を、私たちはどのように理解し、処理していけばよいのでしょうか。ただ単に、競技結果に一喜一憂するだけでよいのでしょうか。現代社会におけるスポーツは、政治・経済・教育などをはじめ、みなさんの想像以上に幅広い分野と関係をもち、みなさんの身近なところにまで影響を及ぼしています。そして、スポーツは、社会や個人に対してプラスに機能するだけでなく、マイナスに機能することもあります。実際にみなさんは、これまでのスポーツとのかかわりのなかで、おそらく良い思い出も悪い思い出ももっているのではないでしょうか。そこで、スポーツの光と影について理解を深め、スポーツが現代社会に生きる私たちにとって、人生を豊かにするものとなるよう、これからのスポーツのあるべき姿について一緒に考えていきませんか。
保護者へのメッセージ
スポーツは、人種や言語、宗教、国籍、性別、年齢などを超えて楽しむことができることから、人生を豊かにするものだといわれます。しかし、スポーツはそれだけではなく、様々な社会問題を解決していく力を養うことができます。例えば、サッカーは手を使ってはいけないというルールがあり、そのなかでボールを上手く足で扱って(コントロールして)ゴールを目指すという非常に困難な挑戦をしていくスポーツです。しかし、競技レベルの違いにかかわらず、サッカーをする人は、それが苦しい、つらい、面倒だと感じることなく、むしろ、どうしたら上手くなれるか、どのように工夫したらよいだろう、などと、その挑戦を楽しんでいます。このようなスポーツによって養われる資質は、社会の変化が激しく、簡単には解決できないような課題が次々に現れ、それらに対して挑戦していくことが求められる現代において、極めて重要になるのではないでしょうか。最近では、スポーツ学生を積極的に採用したいという企業が増えてきているようです。なぜなら彼らは、自ら論理的に考え、新たな取り組みや工夫したトレーニングを取り入れ、かつ、それを楽しみながら実践(挑戦)しているからであり、企業にとって魅力的な人材としてみられているからです。スポーツの学びを通して、社会の様々な問題(困難)に楽しみながら挑戦していくことができるような人材育成に力を注いでいきます。
スポーツ専門演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ(ゼミ)
スポーツ専門演習Ⅰ~Ⅳでは、卒業研究を行い、卒業論文を執筆します。卒業研究を通して養われる研究的視点や思考は、社会人として生活していくうえで大いに役立ちます。また、論文を執筆するということも社会人になって自分の意見や考えを他人に伝える際、大いに役立ちます。これらの能力を、スポーツという興味・関心を通して身につけていきます。
教員の研究テーマ
- スポーツ愛好者を組織化するスポーツ組織研究
- スポーツ組織・スポーツ制度と個人(スポーツ行為者)との関係
- スポーツ社会学、スポーツ組織論、スポーツプロモーション論
これまでのゼミ生の卒業論文テーマ(一部)
- トップアスリートにおけるライバルの存在に関する一考察
:ライバルの存在・不在と競技力向上との関係に着目して - 判定が厳格化する現代スポーツにおけるセルフジャッジの可能性
:アルティメットに着目して - 大学スポーツ観戦を通した一大学の団結力生成の可能性
:競技横断的なつながりと一般学生とのつながりに着目して - スポーツ活動において女子選手が感じる特有の障壁
:男子選手との違いに着目して


